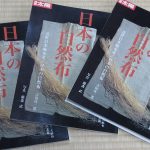しな布はシナノキの樹皮を剥ぎ、糸にして織られた自然布の一つで…
- ブログ -
問屋の仕事場から
- 2017.08.09
- 秘境の織姫がつくる「しな布」 樹皮から糸へ

木の皮を剥いで繊維を取り出したものを「靭皮(じんぴ)繊維」といい、苧麻や大麻もその仲間です。苧麻や大麻は原料を大規模に栽培することができ、糸は機械紡績、織は自動織機を使うことが可能です。低コストで製造することができる一方、それらは原型をとどめておらず、自然の恵とは程遠いものです。
一方、しな布のような素朴な繊維は、加工の機械化が困難ですべて人の手を通して作られています。現物からは自然の産物であることがしっかりと伝わってきます。
大変な手間を要する原始古代布である「しな布」、木からどのように糸にして織られているか解説してゆきます。
しな布は縄文、弥生の太古から原料のシナノキが採れるところでは日本各地で作られていました。その丈夫な繊維は着るものだけではなく、袋物など日用品に広く使われていましたが、綿や麻の伝来とともに瞬く間に生産が途絶え、現在では山形県と新潟県にまたがる山間部の集落(関川、雷、山熊田)で作られています。
集落は最寄りの鉄道駅から徒歩で5、6時間はかかる山奥の僻村にあります。冬季には雪が3メートル近く積り、一昔前までは冬の間は町との連絡が寸断されてしまう所でした。除雪技術が進んだ今でも通行止めになることが珍しくありません。付近にはマタギで有名な集落も存在し、豊かな自然と厳しい環境が同居しています。

山形と新潟にまたがる三つの集落、左から山熊田、雷、関川。 海岸線の町からは20㎞程離れている。 Google Mapより
長い冬に閉ざされた農閑期の間、男達は町へ出稼ぎにいき、残された女達は朝から晩まで機を織る生活が続きます。姑が仕事を辞めるまで嫁は機織りをやめることができなかったそうで、貴重な現金収入としてひたすら織り続けるのが里山の日々でした。
現代ではこのような手間がかかる辛苦な仕事をする若者はいない上、そもそも集落自体の存続が危ぶまれています。現在の作り手も80歳以上の方が中心で、事業継続は厳しい状況です。特に人手(男手)の必要なシナノキの伐採作業が困難になってしまいました。
シナノキは湿気の多い川沿い斜面、渓谷に自生しています。皮が剥ぎやすい梅雨の時期に山に入り、樹皮を剥ぐ作業はお年寄には困難な作業です。今では問屋の社員までも動員しての作業となっています。シナ布作りは織物製造業に分類されますが実態は林業といっても過言ではありません。

川沿いの傾斜地、渓谷など山に自生するシナノキの原木、水分を多く含む梅雨の時期が伐採に適する。
樹皮を剥ぎ、乾燥させ、灰汁煮きをし、発酵、手で績み、機織りをする。他の自然布同様、糸になるまでの工程がほとんどを占めます。この木がどのように糸になるか簡単に見ていきましょう。

皮剥ぎ→乾燥→灰汁煮→発酵→糸績みを経てやっと一本の糸になる。

樹皮をどのように糸に近づけるかというと、裂け目にそって5本の指を使い2㎜幅ほどに細かく裂いていきます。そして裂き終わった繊維の裂け目に次の繊維の根元を挟んで撚りをかけ繋ぐ、しな布の帯一本では400mほどの糸が使われています。

糸が切れてしまっても熟達の「おばあ」が熟達の技で一瞬にして撚りつなぐ。

糸枠に巻かれた「しな糸」、ここまでにするのが工程のほとんどを占める。

現在は高機で織られるが、昔は座機で織られていたとのこと。キャリア50年以上の熟練の腕で織り進められる。
以上、樹木が糸になり織り進められる様子を写真を中心にザックリ(生産者側からしたら失礼なくらい本当に端折って)とみてきましたが、なんとなく糸への変化を分かってもらえたかと思います。
しな布を作り続けるには、良い木を育成し、良い糸を績み、美しく織り上げる技術の継承が必要です。集落ではこの大変根気のいる作業を脈々と引き継ぎ、古来からの製法を可能な限り忠実に守り続けてきました。それは雪に閉ざされてしまう過酷な生活環境と大変な仕事にも耐えうる根気強さがあったからです。
そして高度に現代化が進み、様々な商品があふれかえる日本において、人は本能的に「自然、太古への回帰」を欲し、自然布に懐かしさ、癒しを求めて止みません。はるか縄文時代の人々の素朴な生活を今に伝えられるのは「奇跡」といっても過言ではないと思います。

大昔は漁網にも使われていたほどのシナの繊維、最高の耐久性をもつ。
廣田紬ではしな布をはじめとした古代自然布の良さ、美しさをたくさんの人に広め、楽しんでもらいたいと切に願っています。機会があれば引き続きほかの自然布にも焦点を当て紹介してゆきます。