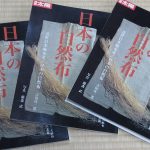35度を超える猛暑日が続く8月、外出時にマスク着用など考えた…
- ブログ -
問屋の仕事場から
- 2020.06.14
- 夏座敷の贅 籐網代の敷物

6月になれば人間は衣替えを行いますが、京町家においても夏仕様に「建具替」が行われます。襖や障子を外して風通りの良い空間作りをしますが、座敷には籐で編まれた網代模様の敷物がお目見えします。
自然布の定義からは外れるかもしれませんが、籐網代の敷物も紛れもない手仕事の工芸品、この機会に紹介したいと思います。
籐(とう)から作られるこの敷物ですが、籐はラタン(マレー語)とも呼ばれる熱帯域に自生するヤシ科の植物です。藤(ふじ)と字がよく似ていますし、素材感は竹とよく似ていますが、全くの別物であることに注意が必要です。日本には自生しておらず、東南アジア(主にインドネシア)などから輸入されてくるものが加工されています。

熱帯域に生息する世界最長のツル性植物である籐、その種類は数百種にも及ぶ。
籐の繊維は天然繊維随一とも言えるくらい強靭なもので、様々な部位が目的に応じて加工され、身近なところでは布団たたきや、家具をはじめ様々な資材に使われてきました。籐でできた椅子も有名で、一度は座ったことがあるかもしれません。最近ではその風合いを樹脂で再現したものがある程です。

海外で民芸品として販売されている籐のカゴ。
籐を使った敷物は、表面にホーロー質のある「セガ」と呼ばれる種類の籐皮が使われています。形状により、籐筵(トウムシロ)と呼ばれるスタンダードタイプと、籐網代(トウアジロ)と呼ばれる高級タイプに分かれます。
籐筵は銭湯などで一度はみたことがあるあの敷物です。
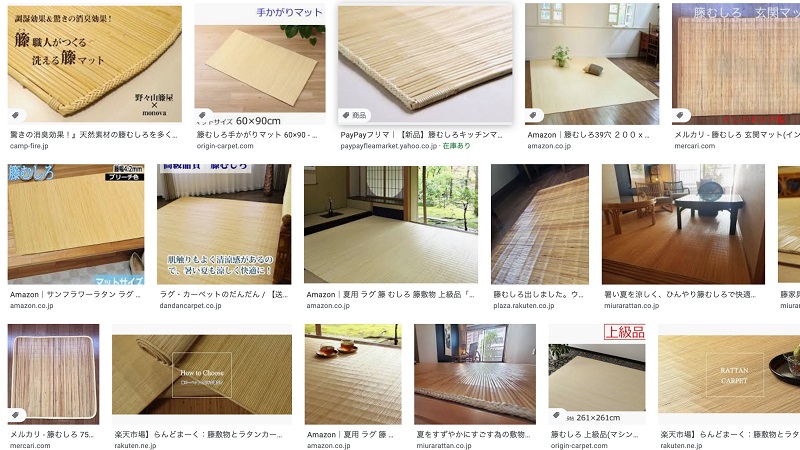
Google検索で「籐むしろ」と検索するとピンからキリまで様々な商品がヒットする。
籐を一直線に並べて糸で繋ぐ、簾のようなイメージです。場合によってはホームセンターなどでも販売されていて、価格もリーズナブルな商品が多いのが特徴です。もっとも、他の自然布と同じく、材料の確保から仕上げまで、手作業の塊の商品であることには変わりなく、コスト競争力に優れた海外産品だからこそ気軽に購入できる価格になっています。
籐筵が民芸品であるのに対し、選別された籐の皮を編み込んで作られる籐網代はまさに工芸品といえます。

中庭から風を呼ぶ構造の京町家、涼しげな夏のしつらえ
こちらは廣田紬社屋の一階座敷、6畳間と8畳間に敷かれている籐網代です。御簾や簾戸(葦戸とも夏障子とも)と相まって、涼しげな夏のしつらえとなっています。
畳も良いですが、ひんやりとした感触と、さらっとした肌触り、藤網代は夏の座敷を飾る主役です。
艶は厳選されたセガ籐の琺瑯質によるもので、艶があればあるほど高級とされ、特級品のみ選別して作られる籐網代は大変な貴重品です。飴色になっているのは経年変化によるもので、1世紀近い歴史が刻まれています。

年季の入った籐網代、爬虫類の鱗のような凄味さえ感じられる。
編み込みの角度が垂直であればあるほど美しく直線を描きます。いかにしてガタガタにならないか、斜めに走らせないか、職人の腕の見せ所です。
組織を拡大、経年に伴うダメージ、表皮の剥がれもありますが、貫入を彷彿とさせるひび割れがなんとも言えません。

経緯の籐皮糸?がしっかりと垂直に組まれているのがわかります。
ちなみにこちらは二階の八畳間に敷かれている籐網代、明るい色でそこまで経年変化を感じられない「比較的」新しいものです。

比較的新しい籐網代、籐皮が菱形に走っている。
一階座敷のものよりも幾分狭角で編まれていて、少しばかり斜めに走っています。両者を比較すると「仕事」としては一階座敷の飴色タイプの方が数段上のクラスであると言えます。こちらは今後数十年かけてゆっくりと飴色に熟成されてゆくことでしょう。

比較的新しい明るい色の籐網代、なかなか一直線とはいかず、ズレが生じている。

組織の拡大、狭角で編まれていることがわかる。
籐網代は畳敷きの部屋のサイズに合わせて作られます。六畳間(京間)でしたら間は10.94㎡という面積なのですが、規格化されているはずの畳のサイズも実はまちまちです。畳の配置にもよりますし、しっかりと部屋のサイズを合わせるのあれば全て別誂となってしまうのです。

部屋に合わせてキッチリ作られた籐網代、蹴つまずかないように金属の板で縁を固定する。
和室が当たり前出会った頃は、業者側もスケールメリットがあったので当たり前のように誂えることができました。現在では現実的でない価格となってしまい、よほどのお金持ち、数寄者でないと作ることができないものです。現在ではその工程のほとんどがインドネシアで行われ、国内では最後の仕上げ(裏打ち、縁かがり等)しかできなくなってしまいました。

設置前の巻いた状態の籐網代、裏には越前和紙が裏打ちされている。
飴色の藤網代はもう作ることのできない貴重なものです。旧家が取り壊されるなどする時に、貴重な飴色の藤網代はバンドバックなどの材料として引き取られていきます。世紀を超えた美しい艶をもつ唯一無二の素材、古い籐網代は高値で取引されているといいます。和室の減少ともに本来の用途として使えないのは少し悲しい気もしますが、和装小物などで新しい人生ならぬ籐生が開けるなら素晴らしいことです。

八畳間に広げられた籐網代、白い小袋は防虫剤。
夏のしつらえは9月後半まで、約3ヶ月しかお目見えしませんが、来訪の際には是非注目してみてください。
※弊社では籐網代、籐筵の扱いはございません。
その後の追記・・・
籐筵について廉価品のような扱いで記載していますが、年季が入ったものは籐網代に負けないくらいの凄みがあります。
廣田紬の社内にあった古い籐筵、

100年以上の時を経てこちらも飴色に変化しています。籐皮の角が取れて丸くなり、スベスベとした素晴らしい経年進化ともいえるものです。
裏側を見てみるとビックリの明治14年(1881年)に新調したとの記載が!

140年も前のものが朽ちず現役で使われている(こちらは年中設置、毎日人が踏みます)ことから籐の驚くべき耐久性が垣間見えました。